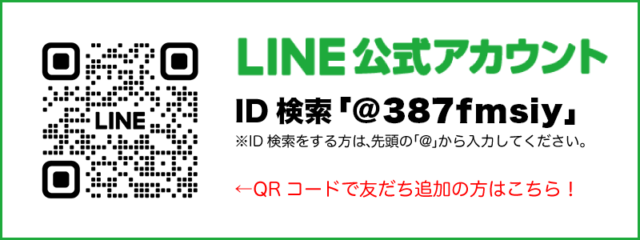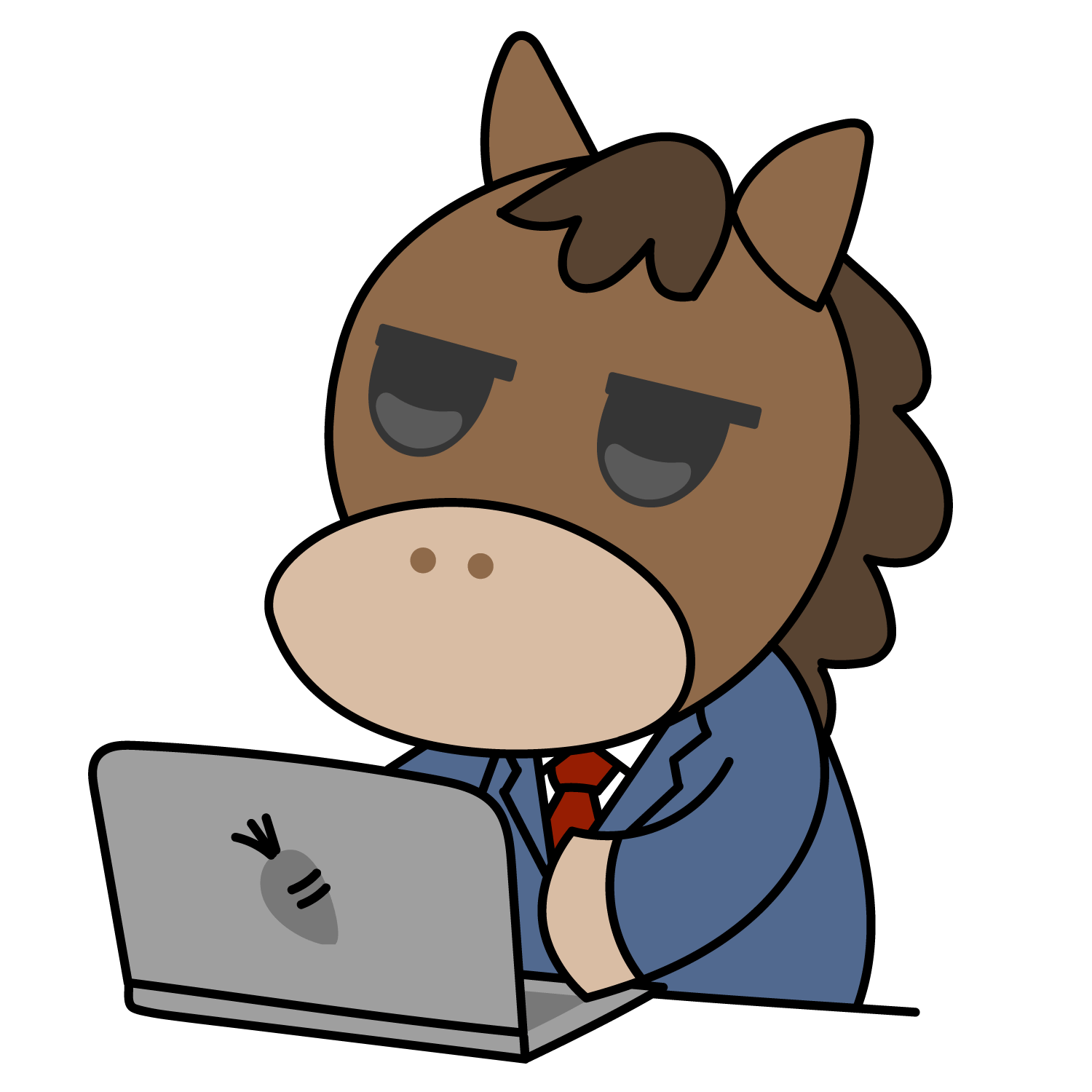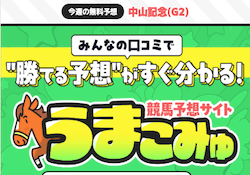地方競馬のクラス分けはこれで完璧!予想に活用できる比較ガイド
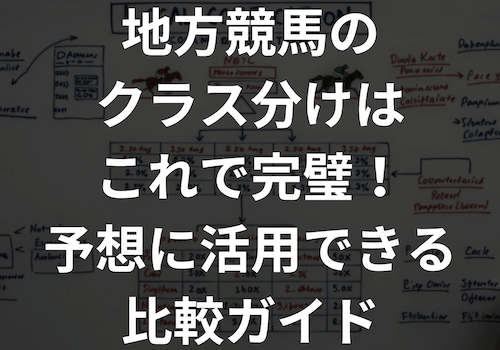
どうも、競馬口コミダービー管理人の木口順一だ。
地方競馬のクラス分けとは、各地方競馬場が競走馬の能力・実績に応じて「A・B・C」などのクラス(階級)に分類する制度だ。
最上位クラス(例:A1級)は「オープン」とも呼ばれ、下位はC級までランクがある。
クラスの決定には各競馬場ごとの賞金獲得額や着順ポイントが用いられ、中央競馬(JRA)のように単純に勝利数だけで昇級する仕組みとは異なる点が特徴。
本記事では地方競馬のクラス分けをテーマに、クラス体系の概要から競馬場ごとの違い、最新データによる傾向分析、そしてクラス分けを活用した馬券戦略まで詳しく解説していく。
地方競馬のクラス分けを理解することで、レースレベルの見極めや予想精度の向上に役立てよう。

- 地方競馬のクラス分けとは?
中央競馬とこんなに違う! - 会場によっても違う!
各競馬場のクラス分け詳細 - 最新データで見る
クラス別勝率と傾向で
予想精度をアップ!
【2025年最新】地方競馬予想ランキング!
競馬口コミダービーでは継続的に地方競馬予想の無料提供のあるサイトの成績を更新し続けている。
地方競馬のランク分けを調べに来た方もぜひ一度目を通してみてくれ。
無料予想の成績をもとにランキング化した地方競馬予想トップ3はこちら。
※右にスクロール可能
| 順位 名前 | 概要 | 成績 的中率 | 利益 平均利益 回収率 | 投資金額 平均投資 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | AIが | 5戦5勝0敗 的中率100% | +188,800円 309.8% | 90,000円 |
| 2位 | ワイドの | 13戦10勝3敗 的中率76.9% | +153,100円 217.7% | 130,000円 |
| 3位 | 20万円以上の | 10戦6勝4敗 的中率60% | +172,200円 272.2% | 100,000円 |
3サイトとも継続して利用しプラス収支を現在も更新中。
どれも登録も予想も無料のサイトで集計を取ったので、各競馬場のランクごとの勝負に慣れるまでの参考におすすめだ。
地方競馬のクラス分けとは?概要と中央競馬(JRA)との違い
それでは改めて地方競馬のクラス分けについて学んでいこう。
地方競馬のクラス分けは馬同士の実力差を調整して、実力が近い馬同士でレースを行うためのシステムだ。
【A>B>C】のアルファベット順でランク付け、Aが最高クラス、Cが最下位クラス(競馬場によって例外的にDも存在)で構成。
さらにアルファベットの後ろには数字(例:A1、B2、C3)を付けて、細かくクラスを区分してあり、数字が小さいほど上位クラスを意味する。
例えばA1は地方競馬のトップクラスにあたり、C3は最も下のクラス。
地方競馬のクラス分けは競馬場ごとに独自のルールで運用されていて、統一されていない。
中央競馬(JRA)の統一されたクラス体系(新馬・未勝利→1勝クラス→条件戦等→オープン)とは大きく異なるので、まずはその違いを押さえていこう。
中央競馬(JRA)とのクラス体系の比較
中央競馬と地方競馬ではクラス分けの方法や運用が大きく異なる。
以下の表に主要な違いをまとめたのがこちら。
| 項目 | 地方競馬のクラス分け | 中央競馬(JRA)のクラス分け |
|---|---|---|
| クラス 体系 | A・B・Cの大きく3区分 細分クラス (例:A1, A2,…C3) | 新馬・未勝利戦から (旧表記: |
| 昇級 条件 | 各競馬場が定める 番組賞金(着順ポイント) 累計により決定。 極端な例では 1着になっても 昇級しない場合や 5着でも昇級する場合がある。 必ずしも 勝利が条件ではない。 | 勝利数に基づき 未勝利戦に勝てば 1勝クラスへ進み、 以降レースに勝つごとに 2勝クラス、3勝クラスと 昇級する (条件戦は勝てば 上がるのが基本))。 |
| クラス 数 | 競馬場により異なるが、 A・B・Cの3区分×細分類で おおむね6~12段階 (例:南関東は A1~C3の8クラス)。 | 全場共通で 5段階+オープン (新馬・未勝利、 1勝、2勝、3勝、 オープン)。 重賞は オープンに含まれる。 |
| 運用 主体 | 各地方自治体・ 主催者ごとに ルールが異なる (統一規則なし)。 ただし南関東4場など 一部地域では共同で 統一クラス編成。 | 日本中央競馬会 (JRA)が全国統一の 基準で運用。 全ての競馬場 (東京・阪神など)で 同一ルール。 |
※地方競馬ではこの他に年齢条件(後述)や交流競走など特殊な条件も絡む場合あり。
上記のように地方競馬はクラス分けの運用に地域差があり複雑だ。
一方、中央競馬は全国で統一された明快なクラス体系を持っている。
例えば条件馬がレースに勝つと必ず次走は上のクラスに上がるのが中央では基本だが、地方では勝たなくても一定の賞金・ポイントを積めば昇級するケースがある点には注意が必要だ。
逆に言えば、地方では連勝でなくても安定して上位入着が続けばクラスが上がるシステムになっている。
クラスが決まる基準と仕組み
地方競馬で各競走馬のクラスを決定する主な基準は以下のとおり。
※右にスクロール可能
| 基準と仕組み | 詳細 |
|---|---|
| 番組賞金 (ポイント) 制度 | 各競馬場では、直近の成績に応じて 「番組賞金」と呼ばれるポイントを付与し、 その累計でクラス編成を行う。 通常は1~5着までがポイント加算対象で、 たとえ5着でもポイントが累積すれば クラスが上がる場合がある。 「1着=昇級」ではない点が特徴。 逆に言えば、 大敗が続けば次開催時に降級(クラスダウン) することも。 各場ともこのポイント制度を基本としているが、 具体的な計算方法や閾値は競馬場ごとに異なる。 |
| 賞金額の 区分 | 一部競馬場では 収得賞金(金額)によるクラス区分も 採用している。 半年ごとに定められた賞金基準で クラスを振り分ける。 獲得賞金上位の馬がA級、 以下順にB級・C級となるイメージ。 賞金基準は馬の年齢によっても異なり、 若い馬ほど少ない賞金でも 高いクラスに編入されるケースがある。 |
| 年齢区分 | 地方競馬では年齢条件もクラス編成に影響します。 いったように年齢ごとに 別のクラス体系が存在する。 例えば2歳馬や3歳馬は 同世代同士のクラス (例えば「2歳A」「3歳B」など)で走り、 一定の賞金を獲得した3歳馬は 古馬混合の「一般クラス」に編入されることも。 各場の番組表で 年齢条件が示されているので注意が必要。 |
| 見直し 時期 | ラス編成の見直し(リセット)は定期的に行われる。 例えば南関東4場では上半期(1~6月)と 下半期(7~12月)で番組賞金の集計期間を区切り、 半年ごとにクラスを再編成する。 年間または半年単位でクラスを見直していて、 そのタイミングで昇級・降級が発生。 新年度開始時(4月)や開催変更時期なども クラスが動くポイント。 |
以上が地方競馬のクラス決定の基本ルール。
一言でまとめると「地方競馬のクラスは各競馬場の定めるポイント(賞金)制で決まり、年齢区分も考慮、定期的に見直される」ということになる。
この仕組みによって、各レースではできるだけ力量が伯仲した馬同士が対戦するよう配慮されていると言えるだろう。
各地方競馬場のクラス分け詳細
地方競馬の競馬場は全国で15ヶ所(平地14場+ばんえい)、クラス分けの名称や細かい段階は主催者ごとに異なる。
ここでは主要な競馬場・地域のクラス分け体系を紹介し、その特徴の違いを頭の中で整理していく。
クラス表記を正しく読み解くことで、出馬表から各馬の力量関係を掴みやすくなるのでマスターしよう。
主な競馬場のクラス区分一覧
以下の表に、地方競馬の主な競馬場・地区ごとのクラス体系をまとめてみた。
アルファベットと数字の組み合わせが各場でどのように設定されているか参考にしてもらえれば幸いだ。
※右にスクロール可能
| 地域・競馬場 | クラス体系(表記) |
|---|---|
| 南関東 4場 (浦和・ 船橋・ 大井・ 川崎) | A1、A2 / B1、B2、B3 / |
| 北海道・ 門別 | A1、A2、A3、A4 / |
| 岩手・ 盛岡・ 水沢 | A / |
| 愛知・ 名古屋 (笠松 含む) | A / B / C |
| 兵庫・ 園田 (姫路含む) | A1、A2 / |
| 高知 | A / B / C1、C2、C3 (上・下) ただしC3級のみ 上・下に分割) |
| 佐賀 | A1、A2 / B / C1、C2 |
| ばんえい・ 帯広 | オープン / A1、A2 / B1、B2、B3、B4 / C1、C2 オープン級を明示) |
※上記の「組」「○組」「一、二…」といった表記ルールについては後述。同じアルファベット・数字でも競馬場ごとに強さの水準が異なる点にも注意が必要だ。
南関東や北海道など競走馬のレベルや頭数が多い地区ではクラスの細分化が多く、逆に名古屋・笠松のように競馬場規模の小さいところでは大まかなA/B/Cの3段階のみで運用されている。
また、高知競馬のように一部クラスだけ特別な区分としてC3級を上位下位に分割するなどのケースも存在。
ばんえい競馬では平地経馬のA1級以上に相当する「オープン」を明治する点が特徴だ。
クラス表記とルールの違いポイント
各競馬場ごとのクラス分けには、以下のような違いや特徴がある。
| クラス表記 | 違いや特徴 |
|---|---|
| 南関東 (浦和・ 船橋・ 大井・ 川崎) | 首都圏4競馬場は 統一されたクラス体系を採用し、 A1~C3まで細かく8段階に分類されます。 さらに各クラス内で「一組・二組…」と 漢数字でグループ分けされ、 番組上は「A2一」「C1二」などの表記が 使われます。 南関は半年毎の賞金額で クラス編成が行われ、 レベルが高いため他地区の A級より層が厚い傾向がある。 |
| 北海道 (門別) | クラスの段階数が最多 (A1~A4、…C4まで計12クラス)で、 細かな力量差まで反映している。 組分けは「○-1、○-2…」と ハイフン付きの数字で表記されている (例:「B2-2」)。 季節ごとの開催休止期間明けに クラス見直しがある。 |
| 岩手 (盛岡・ 水沢) | A級は1段階のみで、 その下をB1・B2、C1・C2に区分している。 組は「一組、二組…」と漢数字表記。 東北地区のトップクラスAは 他地区のB上位相当とも言われ、 南関東交流では苦戦するケースもある。 |
| 東海 (名古屋・ 笠松) | 非常にシンプルで、 A・B・Cの3クラスのみを基本とする。 細かい序列は「○組」 (数字+組)で表し、 例:「B級5組」は Bクラス内で5番目のグループという意味だ。 組番号が小さいほど上位グループになる。 |
| 兵庫 (園田・ 姫路) | 南関東に次いで 細かい7段階(A1~C3)を設定している。 組表記は南関同様に漢数字(「一、二、三…」)。 兵庫では一年を通じてクラス編成が行われ、 開催途中での大きなクラス変動は少なめ。 |
| 高知競馬 | クラスはA・BとC1~C3ですが、 C3級をさらに上下二段階に分けている。 出馬表では「C3(上)」「C3(下)」と表記され、 C2級から降級してきた馬などはC3上に入り、 下位とは隔離されている。 組分けはハイフン数字で「-1組、-2組…」と表示する。 |
| 佐賀競馬 | A1・A2、B、C1・C2の5クラスで、 組分けは「-1組、-2組」とハイフン+組の形式。 九州地区は他場と交流が少ないため独自色が強く、 クラス編成も年1回程度と保守的だ。 これらの違いから、 クラス表記を見るだけで 「どの競馬場・どのレベルのレースか」を 把握することが可能。 例えば「C2三」とあれば 南関東の下から2番目のクラスで 3組目のグループ、「B級5組」とあれば 名古屋などで 中間クラスの5組目という意味になる。 なお、出走頭数確保などの理由で 複数の組をまとめて 1つのレースに編成する場合が ある。 その際はレース名に含まれる組を 全て併記する。 例えば「C3一 二 三」というレース名は、 C3級の一組・二組・三組を 合同で行うことを示す。 また「A4-2~B3」という表記なら、 A4級2組からB3級までの馬を混合した条件戦で。 複数クラスや組が書かれている場合は、 このようにクラスを横断して 編成された特殊なレースだと読み取れる。 |
最新データで見るクラス別勝率と傾向
クラス分けが理解できたところで、実際にレース結果にはどのような傾向があるのかをデータで見ていく。
ここでは最新データや統計を基に、実際にレース結果にはどのような傾向があるのかデータからチェック。
数字を把握することでクラス分けを馬券戦略に活かすヒントが見えてくるので飛ばさないようにしよう。
クラス別の1番人気勝率
まずは各クラスにおける1番人気の勝率を比較。
一般に実力差が起きい上位クラスほど人気馬が信頼でき、下位クラスほど波乱が多いと言われているが、データもその傾向を裏付けている。
| クラス階級 | 1番人気馬の勝率(目安) |
|---|---|
| A級(上位クラス) | 約50%(※安定) |
| B級(中位クラス) | 約40%(※平均的) |
| C級(下位クラス) | 約30% |
※上記は目安の値。実際の勝率は競馬場や開催時期によって異なる。例えば地方競馬全体の1番人気平均勝率は約43%と報告されている。
南関東4場のある年のデータでは1番人気の勝率が約46.8%に達した。
このように上位クラスを多く含む南関東では全体の勝率も高めになっている。
表から読み取れるように、A級戦では約半数のレースで1番人気が勝つ計算に。
一方でC級戦になると1番人気の信頼度は3割程度に低下し、人気薄の台頭する波乱が増えることになる。
実力が拮抗している下級条件ほど予想が難しく、高配当になりやすいと考えていいだろう。
クラスごとの馬券傾向
クラスによってレース結果の出やすいパターンや配当の傾向にも違いがある。
馬券を検討する際、以下のようなクラス別の特徴を頭に入れておくと有利なので確認してみてくれ。
| クラスごとの 傾向 | 詳細 |
|---|---|
| A級レース の傾向 | 上位クラスでは 実績馬・能力馬が揃うため、 人気サイドで決まるケースが多くなる。 実際、A級戦は単勝オッズ1倍台の 圧倒的1番人気が そのまま勝利する展開も しばしば見られる。 配当面では堅く収まりやすく、 3連単の平均配当も低め。 したがって馬券戦略としては 本命馬を軸に据え、 点数を絞って 手堅く狙うのが基本となる。 |
| B級レース の傾向 | 中間クラスでは メンバー構成にばらつきがあり、 人気馬が順当勝ちするレースと 波乱になるレースが混在する。 1番人気の勝率はおよそ4割程度で、 展開や調子次第では 中穴馬の台頭も十分ありえる。 配当はレースによって極端に違い、 本命決着なら低配当、 荒れれば万馬券という メリハリがあるのがB級の特徴。 馬券的にはフォーメーションを 広めに組むなど柔軟な対応が求められる。 |
| C級レース の傾向 | 下位クラスでは 能力差が小さく不安定な要素が多いため、 波乱の頻度が高い。 人気薄の馬が勝つことも珍しくなく、 3連単で高配当 (万馬券以上)が出る確率も 上位クラスより高め。 人気馬も取りこぼしが増えるため、 ヒモ荒れ(2着3着に穴馬)や 大波乱に警戒が必要。 馬券戦略としては思い切って穴馬を絡めたり、 ボックス買いで高配当を 狙ったりする価値があるだろう。 |
見て分かる通り、クラスが下がれば下がるほどレース結果の振れ幅が大きく、配当も跳ね上がる傾向がある。
もちろん例外もあるが「A級=堅め、C級=荒れやすい」と意識しておくと、予想時の資金配分や買い目の組み方に活かせるだろう。
出目ランキング:よく出る数字は?
最後に、「出目」に関するデータも見てみよう。
出目とはレース結果の馬番の並び(着順の数字)のkとおで、「よく出現する数字」や「組み合わせ」の傾向を指す。
直近のレース結果データから、馬番別の勝利回数ランキングを抽出したまとめをみてみよう。
| 順位 | 馬番(1着回数) |
|---|---|
| 1位 | 7番(16回) |
| 2位 | 10番(14回) |
| 3位 | 1番・2番(各11回) |
| 5位 | 8番(10回) |
1位は「7番」、次いで「10番」が多く、「1番・2番」は同程度。
7番は2着の回数でも上位で、もちろんレースごとに出走頭数やコース形態が異なるため一概には言えませんが、「内枠すぎず外枠すぎない中間の枠番」が比較的健闘している傾向がうかがえる。
馬券検討の際、「よく出る出目」を参考にする人もいるが、出目も出目であくまで結果論的な数字の偏りなので、過信は禁物。
レースごとの条件やメンバーを冷静に分析した上で、遊び心として参考にする程度でとどめておこう。
クラス分けを活用した馬券戦略
地方競馬のクラス分けを理解すると、レースレベルの判断や馬券戦略の組み立てに大いに役立つ。
ここではクラス知識を活用した馬券の買い方のコツを、初心者向けと中級者以上向けに分けて整理しよう。
また、クラス変動(昇級・降級)が狙い目になるケースについてもチェックリスト形式で紹介していく。
初心者向け:クラスを理解して馬券を買うコツ
地方競馬初心者は、まずクラス分けを予想の指標として活用するところから始めるべきだ。
以下の5つの指標を利用することで、闇雲に買うより的中率アップが期待できる。
| チェック リスト | 詳細 |
|---|---|
| レースの 難易度を 判断 | 出馬表に記載されたレース名や条件から、 「A級特別」などとあれば 実力伯仲のハイレベル戦、 「C○組」とあれば下級条件で波乱含み、 といったように大まかな難易度の見当がつく。 初心者は最初はあまり荒れすぎない B~Aクラスのレースから手を出すのも一つの手だ。 |
| クラス昇格 直後の 馬に注意 | 下のクラスで勝ったり好走して 今回クラスが上がってきた馬(昇級馬)は、 上位クラスの壁に苦戦する場合があります。 前走圧勝でも相手強化で通用しない例も多いので、 過剰人気には注意しよう。 逆に、下のクラスから上がってきた 馬同士で争うレースであれば、 その中での力比較を重視する。 |
| クラス 降格馬は 狙い目 | 前走まで 上のクラスで走っていた馬(降級馬)が 下のクラスに降りてきた場合、 メンバー中の実績は一枚上だ。 本来の調子さえ戻っていれば 格下相手では能力上位の可能性が高く、 狙い目と言える。 ただし長期間勝てずに降級してきた馬は 調子落ちの可能性もあるため、 近走内容も確認しよう。 |
| 同じ クラスでも 競馬場差を 考慮 | 「B1」「C1」など同じクラス名でも、 開催競馬場によってレベルが異なることがある。 例えば南関東のB1クラスは 他地区のAクラス相当の強さとも言われる。 出走馬が他地区から転入してきた場合などは、 そのクラス名を額面通り受け取らず 背景を読み取ることが大切だ。 |
| 情報量の 多い レースを 選ぶ | クラスが上がるほど 出走馬の過去成績も豊富で情報が多く揃う。 初心者は極端に条件の低い未勝利戦や デビュー間もない馬より、 ある程度クラスが定まった 多く予想しやすいだろう。 クラス分けがわからない新馬戦よりは、 クラス表示のある一般戦から挑戦するのがおすすめ。 |
以上のポイントを踏まえ、「このレースはどのクラスで、どんな馬券傾向になりそうか?」を考えながら予想を組み立ててみてくれ。
クラスを意識するだけでもレースの見え方が変わり、人気馬を買うべきか穴を狙うべきかの判断材料になるだろう。
中級者向け:クラスごとの狙い目と攻略法
さらにクラス分けを深く活用するための、中級者以上向けの戦略をまとめていく。
クラスごとに異なるレースの質や、クラス変動を絡めた高度な狙い目について解説するので確認してみてくれ。
| シチュ エーション | 戦略 | 狙い目 |
|---|---|---|
| 降級馬が 多数いるレース 降りてきた馬が 複数出走) | 前走まで格上で揉まれていた 降級馬は能力上位の可能性大。 条件慣れしていれば 一変が期待できる。 | 降級初戦の馬を 積極的に狙う。 特に前走 上位人気だった馬は このクラスなら信頼度アップ。 |
| 昇級馬 ばかりの レース 勝ち上がった 馬主体の一戦) | 全馬が似たような 条件からの昇級戦なら 力量比較が難しい反面、 前走内容の優劣がカギになる。 | 前走勝ち方が優秀だった馬、 同条件で高タイムの馬を評価。 逆に下級戦ギリギリの 勝利だった馬は割引。 |
| A級の実績馬と 昇級馬が混在 | 実績上位のA級常連馬が 人気を集めやすいが、 昇級馬が軽斤量や 勢いで食い下がるケースも。 | 実績馬が取りこぼすと 高配当も。 格上馬から手堅く流すか、 思い切って新興勢力を アタマに据える穴狙いも一考。 |
| 下位クラスの 混戦模様 実力横一線) | 下位条件は展開や 調子一つで着順が入れ替わる。 波乱前提で組み立てる方が妙味。 | 人気に偏らず、 有力馬のボックスや 手広い三連系で高配当狙い。 近走惜敗続きで そろそろ順番の馬なども拾う。 |
| 他地区からの 転入初戦 クラス表記の変化) | 他場から移籍してきた馬は、 元の所属場でのクラスと 現在のクラスを比較する。 高知A級→南関B級など 見かけ上クラスダウンの場合は 要注意。 | 新天地で相対的に 楽な条件になるケースは 狙い目。 ただし環境適応も考慮。 |
ポイント解説: 上の表にあるように、クラスにまつわる状況ごとに狙い方がある。
特に「降級馬」と「昇級馬」の扱いは地方競馬予想のキモと言えるだろう。
降級馬は能力上位の場合が多く人気でも信頼しやすいが、長期低迷馬の場合は状態次第。
また昇級馬同士のレースでは、下級条件での着差や内容を比較して取捨選択する。
A級戦では実績重視になりがちですが、新鋭の昇級馬が意外な伸びしろを見せることもあり、本命サイドか波乱狙いか判断に迷うところだ。
さらに他地区からの転入馬にも注目しよう。
各地でクラス水準が異なるため、例えば「高知でA級を勝っていた馬が南関東ではB2クラスに編入」というケースでは、クラス表記上は下がっていても依然として強豪相手になる可能性がある。
一方で格上場から格下場へ転入した場合は、クラスこそ引き下げられても実力的には抜けている、ということも起こる。
転入初戦は情報が少ないですが、元の競馬場でのクラス実績と今回の条件を照らし合わせて判断すると良いだろう。
総じて、中級者以上は「クラスの境目」に注目。
クラスが変わるタイミング(昇級・降級・転籍)は馬の力関係が変化する局面であり、他のファンが見落としがちなオッズの歪みが生じることも多々ある。
そのチャンスを逃さず狙うことが、収支アップにつながるだろう。
クラス変動が狙い目となるケース(チェックリスト)
最後に、クラス分けを活用した予想で特に注目すべきシチュエーションを箇条書きでまとめます。
以下のチェックリストに当てはまるレース・馬がいたら、普段以上に注意深く分析してみましょう。

- 前走まで上のクラスに在籍していた降級馬がいる…格下相手で実力上位の可能性。人気でも逆らわないか、軸候補に検討。逆に大敗続きでの降級なら見送り判断も。
- 下のクラスで圧勝し飛び級昇格した馬がいる…勢いは評価するが相手強化で過剰人気の恐れ。昇級初戦は過信禁物で妙味は薄いかも。
- 同じクラスから何度も惜敗している常連馬がいる…クラス慣れしており安定感はあるが勝ち切れないタイプ。人気なら相手までの評価に留め、思い切って他を頭に狙う手も。
- 定期見直し直後(季節の変わり目など)でクラス構成が変わった…新クラスでは各馬の力量差がリセットされ波乱含み。過去の着順よりも能力比較を重視して予想。
- 転入馬が現在のクラスで実績上位と思われる…他地区での戦績次第ではクラス超えの能力に期待。オッズ次第では狙い目だが、環境変化リスクも織り込む。
- オープン・重賞と一般クラスを行き来している馬がいる…重賞実績馬が一般戦に出走してきた場合は明らかに格上。斤量増などハンデあっても軸視。逆に重賞で歯が立たなかった馬の格下戦なら巻き返し期待。
以上のチェックポイントを参考に、クラス変動のタイミングを見極めてみてくれ。
クラス分けは単なる記号ではなく、その馬の置かれた立場や勢いを示す重要なヒント。
状況に応じて臨機応変に活用しよう。
FAQ(よくある質問と回答)

- 地方競馬でクラスが上げ下げするのは
どんな時? - 中央と地方の違いは?
- クラスの変動による
レースへの影響
Q1. 地方競馬でクラスが上がる・下がるのはどんな時?
A1. 地方競馬では各競馬場の定める番組賞金ポイントの累計によってクラス昇級・降級が決まる。
一定期間(例:半年間)で所定のポイントを超えると次開催からクラスが上がり、逆にポイントが伸び悩むとクラスが下がることがある。
勝利は必ずしも条件ではなく、2~5着の積み重ねでも昇級可能なのが特徴です。ただし長期的に大敗が続くと主催者裁量で降級させ、馬の能力に見合った場で走らせる措置も取られる。
また年度替わりや開催区切りで全体見直しされ、順位が入れ替わればクラス変動が起こる。
Q2. 中央競馬(JRA)と地方競馬のクラス分けの違いは何ですか?
A2. 最大の違いは昇級条件と運用の統一性。
JRAでは未勝利→1勝クラス→…→オープンと全国共通の体系で、レースに勝つごとにクラスが上がる明快なルールになっている。
一方、地方競馬ではA・B・C級に分かれたクラス体系で、各競馬場ごとにルールが異なり統一されていない。
昇級も勝利だけでなく賞金ポイント次第で決まるため、中央のような「勝てば即昇級」ではない点が異なる。
またJRAは全国どこでもクラス呼称が同じですが、地方は競馬場によって「A1~C3」や「B級○組」など表記が違う。
ただし趣旨はいずれも「実力が近い馬同士で競走させること」で共通している。
Q3. クラスの変動がレース予想に与える影響はありますか?
A3. そのとおり、クラス変動は予想の重要ファクターだ。
クラスが上がれば相手が強くなるため、それまで楽勝続きだった馬でも通用しなくなる可能性がある。
逆にクラスが下がればメンバー弱化で一変することも期待できるだろう。
したがって昇級初戦の馬は慎重に評価し、降級馬は積極的に狙うなど対処が必要です。またクラス編成が変わる時期(例:半年毎)では力量比較がリセットされ、波乱の起きやすさが変わることもある。
クラス分けを把握することは予想精度向上につながりますし、特に地方競馬ではそれが配当妙味を得るポイントにもなる。
まとめと次のステップ
地方競馬のクラス分けをマスターすれば、レース観戦がより面白くなるだけでなく的中率アップや高配当的中のチャンスも広がる。
ぜひ今回の記事内容を参考に、実際のレースでクラス分け知識を活かしてみてくれ。
あなたの予想が当たり、地方競馬ならではの興奮を味わえることを願っている。
その他おすすめの記事まとめ
※右にスクロール可能
| 記事内容 | 詳細 | 書いてある内容 |
|---|---|---|
| 無料の 地方競馬予想 ランキング | ネット上で無料で見れる 地方競馬の予想の リアルタイムランキング | 急上昇トップ3。総合トップ3。 |
| 地方競馬の 買い方のコツ | 地方競馬の予想をするにあたっての 買い方のコツ | 基本セオリー。 精度アップのための7つのコツ。 参考に使えるサイト集。 |
| 地方競馬で 勝ちやすい場所 まとめ | 全国に存在する地方競馬会場。 | 勝ちやすい競馬場の定義。 |
| 地方競馬の 万馬券 確率 | 地方競馬で万馬券を狙うにあたって | 平均配当まとめ。 |
競馬口コミダービーのLINE公式アカウントが遂に始動!